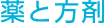〈 第4回 〉
人体がさまざまな外邪に襲われたばかりの最初の状況を、『傷寒論』では「太陽病」と称している。病がうまく治らないと変化してさらに「陽明病」、「少陽病」、「太陰病」、「少陰病」、「厥陰病」と変わってゆく。浅い「表」から深い「裏」まで、陽から陰に浸入してゆく変化を「六経病」の伝変として把握した。人体が受けねばならない外感疾病の襲来を、このように三陰三陽で表される「六経病」という卓越した考え方で対応した古人の見識には驚くほかない。この考え方は「六経弁証」というしっかりした方法に生長している。ところで最初の太陽病には傷寒、中風と二つの強弱のパターンがあって、注意深く分けて論じられている。その一つの「中風」は勿論現在誰もが「脳血管障害」の呼び名として使われる意味ではなく、文字通り毒に あ 中たるのが中毒という具合に風(邪)に あ 中たったというわけだ。同様に寒にやぶ傷られたのが傷寒である。傷寒と中風では、中風は邪がすこし軽く、傷寒は比べてやや重い。前回に桂枝湯についてお話ししたようにかぜをひいてすぐに汗がでやすいもともと体表を防御する衛気のよわい人、よわっている人のかぜに用いてよく効く方剤だが、一方傷寒の方は一段と本格的なかぜのことだ。「太陽病、或いはすでに発熱し、或いは未だ発熱せず、必ず悪寒し、體痛、嘔逆、脈陰陽とも倶に緊の者は、名づけて傷寒という。」と原典の言葉にあるように中風のおだやかな症状と比べると悪性の激しい症状を過不足なく的確に言いあらわしている。急性の肺炎とかインフルエンザのような病気の初期の症状を思い描いてみればうなずける。私はインフルエンザがはやる季節にはその手のお客さんが来ないかとひそかに待ちかまえている。いよいよあらわれると待ってました、とばかりとびかかる。医者でないから診察も診断もできないが、きっとインフルエンザではないですかといってこれが家族とか友人ならすばやく脈をみる。「浮」の脈もしっかりとることができる上、ぐっと強く按じると深いところにも力のある緊張した速脈をたしかめることができる。「脈陰陽とも倶に緊の者」という状態だ。「体中のふしぶしが痛みはしませんか」ときくと「腰がガクガクするし、さっきからむかつきもある」という。この嘔逆はしばしばみとめられることだが、太陽病の次に変わってあらわれやすい「少陽病」の大事なサインが嘔であることから見まぎらわしいように思われるがこの際の嘔逆はその熱のあまりの激しさのあらわれに他ならないことを納得すれば見分けはたやすい。この時が「麻黄湯」の出番である。
今は嫁いで3児の母になっている私の娘がまだ保育園に通っていた頃、ひどいかぜで40度近い熱が続いたことがあった。私は熟慮して麻黄湯のエキスをお湯にといてのませた。2回3回とのませたが熱は下がらない。病人の枕もとで『傷寒論』を読めといわれるとおりにしても私に考えられるのは「麻黄湯」を措いてなかった。そこで「麻黄6g、杏仁5g、桂枝4g、甘草2g」をはかって鍋で煎じて大人量の1/3をのませた。30分もじっと見つめていると何とも知れず険悪な、いやな表情の寝顔がいつとはなふだんの穏やかな顔つきになったのがわかった。「ありがたい!」と私は思った。それからほんのしばらくして娘は不意に両手を大きく使って着ていたふとんをはねのけた。ちょうど蒸し器のふたを取ったみたいだった。まっすぐ上に湯気が吹きあげたのだ。すでにねつは下がり、私は麻黄湯の効き目に讃歎すること限りないというありさまだった…。
このように、太陽病傷寒の方剤の代表はこの「麻黄湯」なのだが上記のようにたった4味の鋭い斗士という感じの処方である。ここにも桂枝湯に用いられた桂枝が加わってくる。しかし今度は麻黄の力をいっそう強め、発汗を充分に行うために用いられるのである。配合の妙ははかりしれない…。麻黄を用いる同類の処方にはなお大青竜湯、葛根湯、越婢湯、小青竜湯などなどとたのもしく連なっている。なかでも葛根湯―これがなかなかのユニークな方剤である。
(この項続く)
(広報誌「清流」第51号(2000.9.20)より)