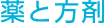〈 第3回 〉
桂枝湯は桂枝4g、芍薬4g、大棗4g、生姜4g、甘草2g、生姜は生のひねショウガを用いるか乾燥したショウガを1g用いてもよい。水500mlで煎じて半量に煮つめ滓を濾し去って3回に分けて温服する。そのあと熱い稀い粥をすすって薬力を助ける。ふとんをかぶって温かくして臥して、全身から汗がにじむようにするのがよく水が流れるように汗を出してはいけない。さらに食事の注意まで加えてまことに何から何まで手厚い指示が尽くされている。
桂枝湯の大棗に甘草、生姜は処方のしめくくりに用いられるおなじみの三点セットでひとまず置くとして、問題は桂枝と芍薬の二つだけだ。これなら覚えるに苦労しない。桂枝、芍薬、大棗、甘草、生姜。かくして我々は漢方の数知れない処方のルーツともいえる、大事な処方─桂枝湯を覚えてしまったわけだ。『傷寒論』の中に111の処方が挙げられているが冒頭に挙げられているのが他ならぬ桂枝湯である。
このことについて、現在中国漢方医学界の重鎮の一人である劉渡舟先生の『中国傷寒論解説』の中には、次のように述べられている。「ここで指摘しておかなければならないことは、張仲景が桂枝湯を『傷寒論』の最初に挙げているのは、何も偶然のことではない。治病の原則は、陰陽の調和にあることをいうためである。桂枝湯は滋陰と和陽をはかる処方であり、このために群方の魁とされる。これは第7条の、病の陰陽に発するを弁ず、の考え方と同等に重要な意義をもっている云々…」
何度も繰り返して気がひけるが、中医学が私どもに人体を把握する要諦を繰り返し説いて、あるいは気血といい、あるいは営衛といい、あるいは表裏というがいずれも皆陰陽の別の言い表し方に他ならない。桂枝湯の話をする時には、特に営衛という表現がもってこいではないかと思う。この「営衛」という表現は、就中、外敵の襲来に出くわした、さあ大変という時の人体の状況を理解しようとする時に最もふさわしい、説得力をもつ表現であろう。本には「営気は血と共に脈の中をめぐる気(エネルギー)であり、衛気とは脈外をめぐる気(エネルギー)である。」などと説明さあれてあって面食らうが、ナニかまわないで、ここでは衛(衛気とか衛陽ともいう)は主に外の外邪(風邪、湿邪、インフルエンザウィルス等々)に対する防衛機能を受け持ち、いわば夫婦でいえば旦那の役目、一方栄(営気とも営血ともいう)は体の内にあって血を生成し全身を栄養、滋潤する、いわば家庭を守る奥さんに相当する役目を果たしている。このようにして営衛調和していればよいがここに外邪の侵襲がおきた時、どうなるだろう?仲景師はそれを次のように描いておられる。「太陽の中風、脈陽浮にして陰弱、嗇嗇として悪寒し、淅淅として悪風し、翕翕として発熱し、鼻鳴、乾嘔の者は、桂枝湯之を主る」これは要するに風邪の外襲によって安定していた営衛の調和が乱される状態こそ、桂枝湯証のモデルなのだ。仲景師はその著書の冒頭に於いて人間の体と薬方とのかかわり合いを最も理解しやすい原形を示して見せておられる。
桂枝湯がその対応する人体の仕組みを浮きぼりにし、また体の仕組みが桂枝湯の成り立ちを導きだしているという按配だ。人体の陰と陽、衛と営は桂枝湯の桂枝と芍薬に反映される。桂枝の作用は発汗解肌、通陽化気といわれる。撹乱されてすくんでしまった体表の衛気を元気づけ陽気を回復してやる。体表の衛気の失調に呼応して外に洩れ、正気不足をあらわす営血のおとろえを芍薬が補血、補陰作用によって救援に向かう。こうして営衛の調和は再び取りもどすことができる。
まことに人体が営衛の調和の中に安らいでいるのは実に柔和な状態であり、その反映である桂枝湯も見れば見る程、バランスのよい温和な薬方と思われる。妙な連想で笑われてもしかたないが私はイエスの言葉を思い出してしまうのだ。「幸いなるかな、柔和なるもの。彼らは地をうけ嗣ぐであろう。」どうやらそのようにして桂枝湯と、それをルーツとする漢方薬方の一族は二千年も絶えることなくうけ嗣がれて来ているようではないか。
桂枝湯は柔和な薬方なのは確かだが、あまり使うことがないかというと決してそんなことはない。残念ながら紙数が尽きたので又次の機会にでもお話しさせて下さい。
(この項おわり)
(広報誌「清流」第49号(2000.6.20)より)