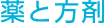〈 第2回 〉
漢方を学んだり応用したりしようとするものにとって、この医学の原点に『傷寒論』という書物が与えられたことは何ものにもかえがたい幸せなことであった。なぜなら延々2000年もの時間を揉みぬかれても、金剛のように不変の方針とセオリーが手に入ったからである。例えば、さらに300年くらいさかのぼることになるが、西洋医学の父といわれる偉大なギリシャの名医ヒポクラテスが、医者の道徳を提唱した有名な「ヒポクラテスの誓い」は現代でも世界中のお医者の心に生き続けているけれども、ヒポクラテス師の用いられた処方が今も使われるということは考えることもできない。ところが我が国で現代の最先端の医療の中で『傷寒論』中の処方が、それこそ一味もさしかえられることなく用いられているのだ。
『傷寒論』という書物はそこを原点とするこの医学に、このように息の長い発展を可能にする見取図、人間と疾病との関係を解き明かし、2000年を経ても変更することも修正することも全く必要としない驚くべき治療ガイドラインを提示しているのである。張仲景というこの稀有な医人は、本国の中国でも厚い尊崇を集め医聖として讃えられているのは勿論であるが、どういうわけかわが国でも又昔から格別の敬愛と恭順の誠を捧げている著名な医師は枚挙のいとまがないくらいで就中傷寒論の解説書まで著してしまった人も多い。私の先生、大塚敬節先生も実にわかり易い『傷寒論解説』を書かれ、わが本棚を出たり入ったりしながら私を教導して下さっている。ついでながらその序文のところで紹介されている江戸時代の名医宇津木昆台の傷寒論讃辞をひきうつしてみよう。「天地ありてより以来、未だかくの如き妙文を見ず。聖作に非ずんば誰かこれをよくせんや。」大塚先生は続けて「昆台のいう如く、傷寒論に匹敵する医書は空前であり、絶後であるだろう。漢方の古典でも、この書に比肩し得るものは絶無である」といわれる。大塚先生が友人として一目も二目もおいておられた傷寒論研究家で薬剤師の荒木性次先生の「初夢は仲師と山へ薬採り」の句など、日本のとりわけ古方家の愛すべき片鱗をうかがわせて妙ではないか。ちなみに荒木先生は山野を跋渉してなるべく御自分で採集して来られた薬草を使って漢方薬を調合されていた。先生の『新・古方薬嚢』は特に我々薬剤師にとって、とりわけよいアドバイスに充ちたテキストである。
さて、本題にもどるとして『傷寒論』というのはすこし詳しくいうと『傷寒論』と『金匱要略』の二篇が合された『傷寒雑病論』という本のことであり、この中に全部で375の処方が掲載されている。そのうち『傷寒論』では113処方、『金匱要略』には262処方が紹介されている。この傷寒金匱に掲げられた処方は古方と呼ばれていて、古方派の漢方家たちはこの限られた処方だけを用いて万病に立ち向かっていく。この潔癖な人々が無視して用いることはない後世方と呼ばれる古方以外の漢方処方はいったいどれくらいあるのだろう。「その方剤数の多さにはまさに閉口してしまう。宋代の『太平聖恵方』では100巻の中に16.834処方、『聖剤総録』200巻中に20.000処方、明代の『普済方』426巻中に61.739処方もの方剤がある。云々」(南京中医薬大学講師・黄煌著『十大類方』より引用)
優れた中医師であり中国政府派遣留学生として京大の医学部に在籍された折りに書かれ、日本漢方の指導的な役を果たしてこられた医師坂口弘先生の序文が巻頭に載っている、『十大類方』からの引用を続けてみると、「これほど多くの方剤を詳しく把握することは不可能であり、またその必要はない、なぜならキーポイントとなる方剤は数十処方にすぎないからである。これは漢字の字源、英語の語根と同様、何万という方剤の基本的構成を成すもので著者は「方根」と呼んでいる。
それでは「方根」はどこに存在するのか。それはまさに『傷寒論』、『金匱要略』の中に存在する。この二書の処方は張仲景一人によって創製されたものではなく(『傷寒論』の序文に仲景師みずから"ひろ博く聚方をと采り"と述べておられるように)漢代以前の用薬経験を総括したものであり、かつ後世の無数の医家達により臨床で検証され認識されうけつがれてきたものである。─中略─ 後世に於いて名医と呼ばれる医家は数多いが、彼等の臨床における規範はすべて張仲景の学術範囲を越えてはいない。それ故"仲景の方、およ最そ群方の祖と為す"(成無已)"仲景の薬万世の法となす"(張元素)"仲景の諸方、実に万世医門の規矩準縄(お手本とか規則とか心得とかいうこと)となす"(朱丹溪)などの言葉が残されている。云々」
この度はやたらに紙面を費やして誠に心苦しいのだが、苟も漢方をかじったものなら、たいてい『傷寒論』の熱烈なファンにならない人を知らない。でも、これでようやく『傷寒論』冒頭を飾る"桂枝湯"についてお話しする段取りができた。これがまた、聚方の祖(ルーツ)としていわくある名方なのだ。
(この項つづく)
(広報誌「清流」第48号(2000.3.20)より)