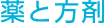〈 第1回 〉
もうすこし続けて書いてよいとお許しがあったので、またしばらくご辛抱お願いしたいと思う。しおらしいことを言っても、カラオケのマイクではないが、一度握らせたら最後なかなか手放そうとはしないたぐいのようで気がひけるのだが、前回までが曲がりなりにも総論とすれば今度は各論を少しばかり書かせていただきたい。30年あまりも虚仮の一心でしがみついて来たおかげでお話しするテーマにはことかかない。
さて、漢方における薬物の勉強には現代科学の方法、つまり有機・無機化学の精緻な分析法によってあきらかにされる成分、又それらの漢薬の生理学・病理学の実験室での動物実験によるデータから導かれる作用の認識などは、当面あまり役立てられているようには思えない。ベジタリアンが肉を贈られたようなもので当惑するほかないという感じだ。現代の生薬学の本をひもといてもその広汎な知見がすぐすぐには助けにはならない。漢方における薬物の理解には、その薬物が人間にどのようにかかわるか、もうすこし詳しくいえば人間の病理反応にどのようにかかわるか、病んだわれわれ人間の苦痛をいかに軽くしてくれ、ぬぐい去ってくれるかだけにかかっている。こうして選ばれた薬物に「本草」という敬称を奉って、せっせと研究してきたのである。「本草」とはいってもこの中にはミミズ(地龍)やカキガラ(牡蠣)から代赭石のような鉱物も含まれる。まず「気味」という素性調べをしなければならない。もっともこの作業はほとんど先人がクリアしてくれている。何しろ2000年前の中国に著された本草書(薬物学書)でその名も『神農本草経』の頃から用いられてきた概念なのだ。
この古典は御存知の先生方も多いと思うが、そこにとりあげられている薬物は365種類でそれぞれについてその「気味」が明確に記載されている。「薬には酸鹹甘苦辛の五味と、寒熱温涼の四気、及び有毒・無毒がある」と気味について説明されている。漢方におけるこの薬物観は成熟を遂げて現在、より確固とした重要な概念となっている。「薬証」とも言われ、その薬物の使用基準であり、その薬を使用する際の根拠となるもの、またその薬物の「主治」とも称される。「この使用基準と根拠は理論的に推測されたものでも、また動物実験によるデータにより得られたものでもなく、中国人の数千年に及ぶ疾病治療における経験の結晶であり、中国人が自らの体を実験台にして得られた結論なのである」(黄煌著・中田敬吾監訳『張仲景50味薬証論』より引用)
漢方を学ぶ場合まずその素材になる薬物の「薬証」を深く把握するのがオーソドックスな、従って最も効果的な方法であるにちがいない。「薬証」についての黄煌先生の長い論述をここでそっくり紹介することはとてもできないので私なりの要約をさせていただきたい。薬証(又広く漢方医学のキーワードのようにしきりにあちこちで口にされる「証」という言葉も含めて…まるで捕り物映画の中で口々に叫ばれるあの"御用!""御用!"みたいに漢方といえば"証!""証!"だ)とはいったい何なのか。黄煌先生は縷々述べられたあとこう位置付けられている「…薬証は症状によって構成されることにより、「人」の病理反応を反映しているのであり云々…」すなわち健康な状態に証はないが人が疾病により病理反応を起こすと、ちょうど写真のネガとポジを見くらべるとわかるように薬証と病理反応は互いに相手を浮かび上がらせているといえる。これは漢方医学の最もユニークな特徴である。黄煌先生は続けて「『傷寒論』『金匱要略』における用薬法は極めて厳格であり証があってはじめて薬を用いる。証がなければ薬も存在しないのであり…」といわれるように、これをもっとつきつめて考えると薬証や証の理解と認識を極めてゆくならば逆に我々の体の病理反応が示唆されるという奇妙なこともあり得るわけだ。我々の体が起こすいかなる病理反応もそれに対応する薬証が待ちうけていないものは一つもないという結論になる。
(この項つづく)
(広報誌「清流」第47号(1999.12.20)より)